【初心者向け】絶対に知っておきたい保険の基本|失敗しない選び方のコツ

こんにちは。私は48歳、自営業で一家を支える父です。
ファイナンシャルプランナー2級・証券外務員1種・宅建士の資格を持ち、普段からお金に関する相談を受けることがあります。
「保険に入った方がいいのはわかるけど、種類が多すぎてよくわからない」
「勧められるままに契約して、保険料が高くて家計を圧迫している」
そんな声をよく耳にします。実は、保険は選び方を間違えると「安心」ではなく「家計の負担」になってしまうのです。
今日は、初心者の方が失敗しないために知っておきたい保険の基本と選び方のコツをお伝えします。
なぜ保険に入るのか?保険の本当の役割
保険の役割は「万一のときに家計を守ること」です。
- 医療費が高額になったとき
- 世帯主が亡くなったとき
- 働けなくなったとき
こうしたリスクに備えるのが保険です。
一方で、「なんとなく不安だから」と保険を増やすのは失敗のもと。
公的制度(健康保険・高額療養費制度・遺族年金など)があるため、民間の保険はあくまで不足分を補う役割と考えましょう。
初心者が知っておくべき保険の種類
保険には大きく分けて3つのジャンルがあります。
1. 生命保険
世帯主に万一があった場合に、残された家族の生活費や教育費を補うための保険です。
- 定期保険:一定期間のみ保障。掛け捨てだが保険料が安い
- 終身保険:一生涯の保障。貯蓄性がある分、保険料は高め
初心者向けのポイント:必要な保障額を算出し、必要な期間だけ定期保険で備えるのが基本。
2. 医療保険
入院や手術の際に給付金が出る保険です。
ただし、日本には「高額療養費制度」があるため、医療費の自己負担は一定額に抑えられます。
初心者向けのポイント:過度な保障は不要。日額5,000円程度で十分な場合が多い。
3. 損害保険
自動車保険・火災保険・地震保険など。生活に直結するリスクに備える保険です。
これらは必要性が高いため、必ず加入を検討しましょう。
初心者がやりがちな失敗(NG行動)
❌ 勧められるままに加入する
営業担当者に提案されたまま契約すると、自分に不要な保障までつけてしまいがちです。
❌ 保険料を「積立」と勘違いする
「将来返ってくるから安心」と思って加入した終身保険や学資保険が、実は利回りが低く、資産形成には不向きなこともあります。
❌ 保障額を考えずに「とりあえず入る」
必要な金額を計算せずに加入すると、保険料が高すぎて家計を圧迫します。
失敗しない保険の選び方5つのコツ
① 公的制度を確認する
まずは健康保険・高額療養費制度・遺族年金など、公的保障でどこまでカバーされるかを理解しましょう。
それを踏まえて「足りない部分だけ民間保険で補う」という考え方が基本です。
② 必要保障額を算出する
生命保険に入るときは「万一のときに家族にいくら必要か」を試算します。
例)子どもが2人、住宅ローン残高ありの場合:
- 教育費:1,000万円
- 生活費:月20万円×10年=2,400万円
- 住宅ローン残債:2,000万円(団信加入なら不要)
合計で必要なのは3,400万円程度。これをベースに定期保険を選ぶ、といった形です。
③ 保険料は「手取りの5〜7%以内」に
保険料が高すぎると、家計を圧迫して本末転倒です。
手取り月収の5〜7%以内に収めるのが無理のないラインです。
④ 掛け捨てを恐れない
「掛け捨てはもったいない」と思う方が多いですが、保障は万一のときに役立てば十分価値があります。
貯蓄や投資は別口で行う方が効率的です。
⑤ 定期的に見直す
ライフステージに応じて必要な保障は変わります。
- 子どもが独立 → 教育費分の保障は不要
- 住宅ローン完済 → 団信保障があるので死亡保障を減らせる
5年ごと、または大きなライフイベントごとに見直しましょう。
我が家の実例
私も以前、保険を「貯蓄代わり」として考え、終身保険を契約していました。
しかし、利回りを計算すると銀行預金と大差なく、資産形成には効率が悪いことに気づきました。
その後、終身保険を解約し、必要最低限の定期保険+医療保険だけに絞りました。
浮いた保険料は「つみたてNISA」に回し、老後資金の準備を始めています。
結果、毎月の固定費が下がり、資産形成も加速しました。
まとめ|シンプルに考えれば保険は怖くない
保険の基本をまとめると次の通りです。
- 保険は「万一に備える」ためにある
- 公的制度を確認して、不足分だけ加入する
- 保険料は「手取りの5〜7%以内」に抑える
- 掛け捨てを恐れず、貯蓄・投資は別枠で行う
- ライフステージごとに見直す
難しく考える必要はありません。
保険をシンプルに整理すれば、安心と家計のゆとりの両立ができます。
お父さん、今日からぜひ「保険の見直し」を始めてみませんか?
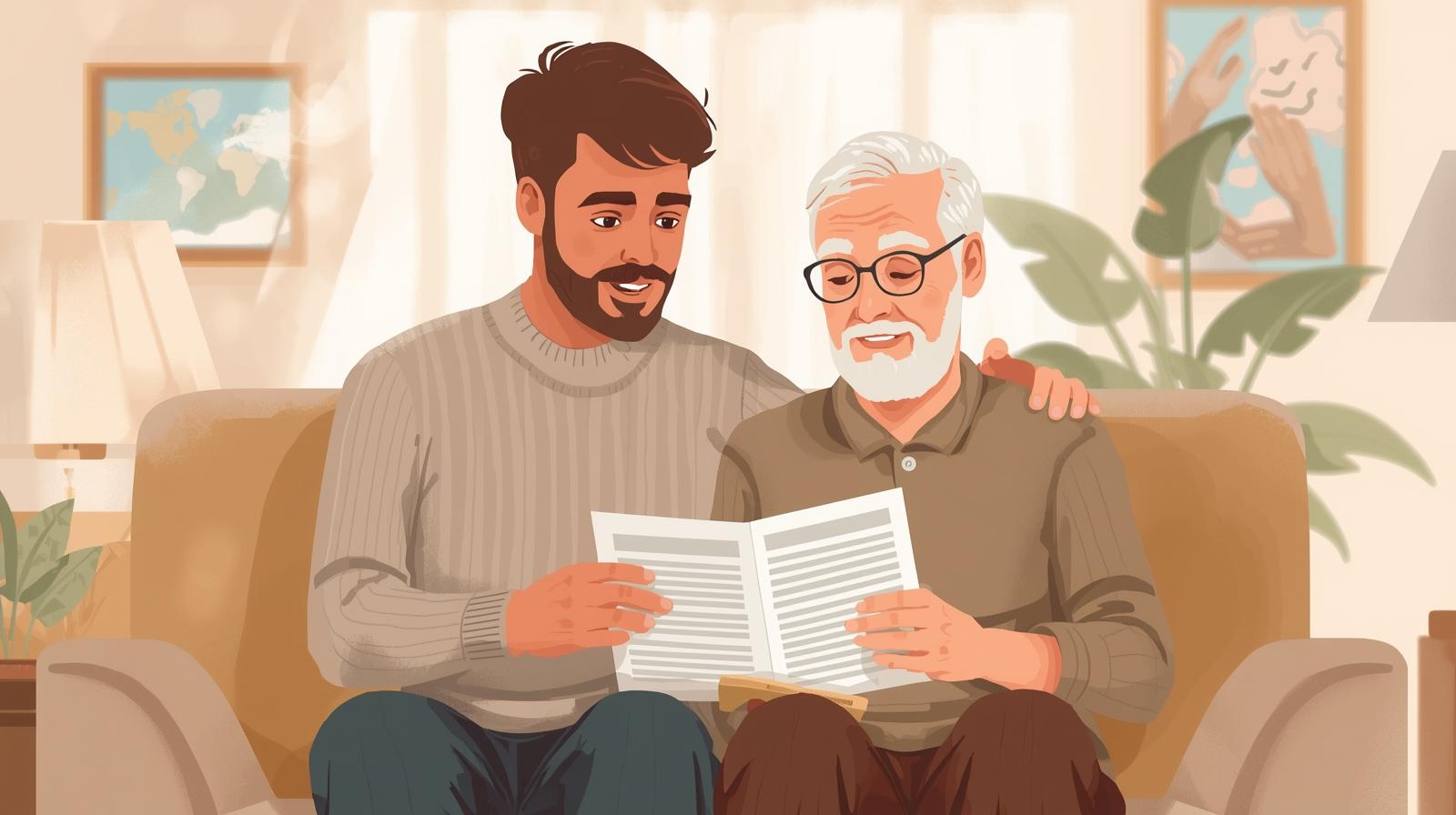
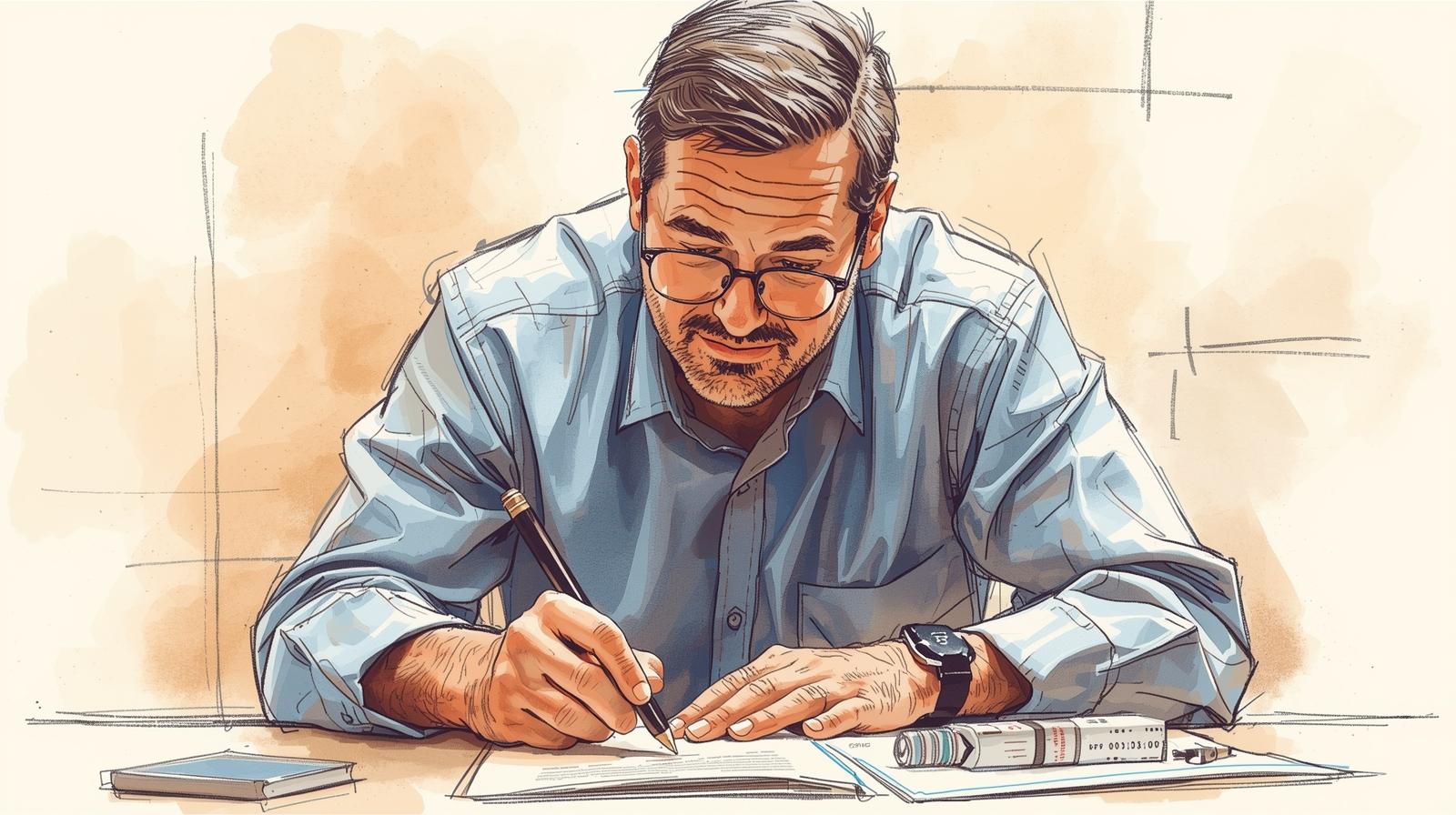





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません