【実例つき】教育費はいくら必要?
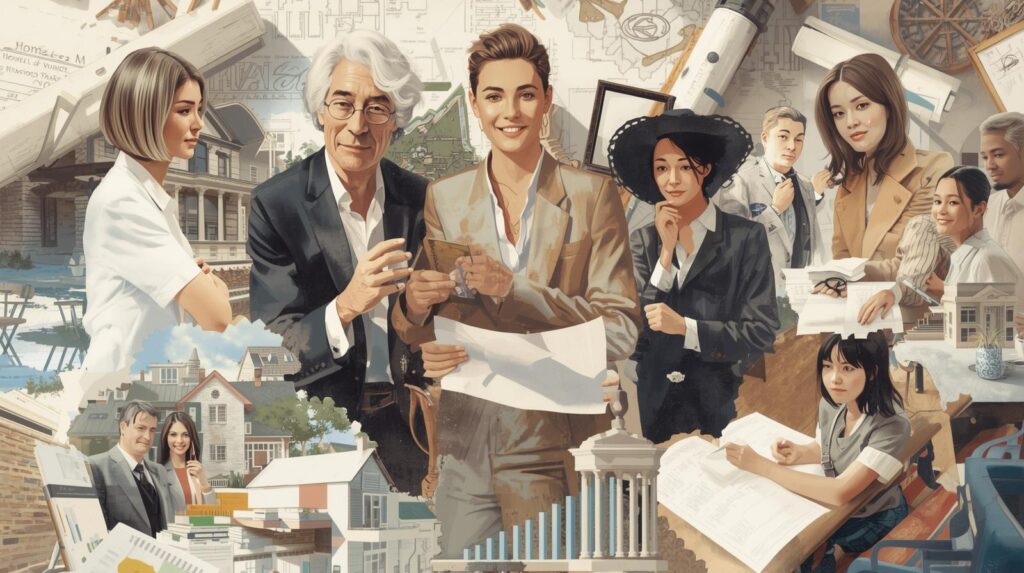
──お父さんが無理なく備えるための家計戦略
「子どもの進学費用、正直いくらあれば安心なんだろう?」
そんな漠然とした不安を抱いたことはありませんか?
ニュースでは「大学までに1,000万円以上かかる」と聞くけれど、
現実には毎日の生活費、住宅ローン、老後資金…
どれも削れない中で、“教育費の準備”はつい後回しになりがちです。
48歳、自営業で一家を支える父であり、
ファイナンシャルプランナー2級・証券外務員1種・宅建士を持つ私も、
まさに同じ悩みを経験してきました。
今回は、FPとしての知識と父親としての実体験を交えながら、
「無理せず教育費を準備する現実的な方法」をお話しします。
教育費の“総額”をざっくり把握しよう
まず、教育費を考えるうえで最も大切なのは「全体像を知ること」です。
文部科学省の調査によると、
子ども1人あたりの教育費の目安は以下の通りです。
| 教育上の優秀さ | 公立の場合 | 私立の場合 |
|---|---|---|
| 幼稚園~高校まで | 約540万円 | 約1,800万円 |
| 大学(4年間) | 約500万円 | 約700万〜1,000万円 |
つまり、大学進学までトータルで
公立コース:約1,000万円/私立コース:約2,000万円 程度が目安です。
もちろん、すべてを“現金で”用意する必要はありません。
ただ、今どこにいて、どのルートを想定しているのかを“見える化”することで、
焦りが“安心”に変わります。
貯金よりも“積立”が効果的な理由
「教育費=貯金」と考える方が多いですが、
実は貯金だけでは間に合わないことが多いのが現実です。
教育費は10年・15年という長期の支出。
そのため、銀行預金よりも
“積立×時間”を味方にする方法が有効です。
代表的なのは以下の3つ。
- 学資保険
→ 返戻率は低いが「確実に貯まる仕組み」として安定。 - つみたてNISA
→ 教育資金を運用しながら積み立てる。リスクはあるが時間を味方にできる。 - 定期預金+ボーナス併用
→ 低リスクで着実。目標年数と金額を明確にするのがコツ。
私の場合、子どもが小学生に入ったときから「つみたてNISA」で毎月1万円をスタート。
途中、相場が下がった時期もありましたが、
5年以上続けた今、元本+運用益で約100万円になりました。
“少しでも続ける”ことが、最大の武器です。
教育費のピークは「大学入学前後」
多くの家庭で“教育費の壁”になるのが大学入学前後です。
入学金・授業料・一人暮らしの準備費用などが一気にかかり、
一時的に100万円以上の支出が必要になるケースもあります。
その時になって「貯金が足りない」と気づく人が多い。
だからこそ、
「高校在学中にどれだけ準備できるか」が勝負です。
FPとしての視点から言えば、
“大学入学時点で100万円を確保” がひとつの安心ライン。
この金額を10年で積み立てるなら、
月々約8,000〜9,000円の積立で到達可能です。
数字にすると、意外と現実的に感じませんか?
無理なく備えるための家計リセット術
教育費を確保するために“節約”だけに頼ると続きません。
おすすめは、支出の「優先順位」を整理することです。
✅ ステップ1:固定費を削る
通信費・保険料・サブスクを見直す。
月5,000円の削減でも、年間6万円、10年で60万円。
✅ ステップ2:臨時収入を教育費口座へ
ボーナスや確定申告の還付金など、“臨時収入は使わず貯める”。
心理的負担が少なく、モチベーションを保ちやすいです。
✅ ステップ3:家族で共有する
「教育費の目標」を家族で共有し、
夫婦で管理アプリを使って見える化すると、
支出に対する意識が変わります。
FPが伝えたい“焦らない準備”の大切さ
教育費の準備で最も大切なのは、
「焦らない」「他人と比べない」ことです。
SNSを見ると「○○万貯めた」「投資で教育資金を増やした」という情報が流れますが、
家庭の状況はそれぞれ違います。
重要なのは、“続けられる仕組み”を作ること。
大きな金額を一気に用意しようとせず、
月々の積立で“未来の安心”を少しずつ育てていきましょう。
まとめ:子どもの未来は“今日の一歩”から
- 教育費は「全体像を見える化」して把握
- 貯金よりも「積立×時間」で備える
- ピークは大学入学前後。目安は100万円確保
- 無理せず、家族で共有しながら続ける
お金の準備は、愛情の形のひとつです。
無理なく続けられる計画こそが、
お父さんにとっても、子どもにとっても“最高の安心”になります。

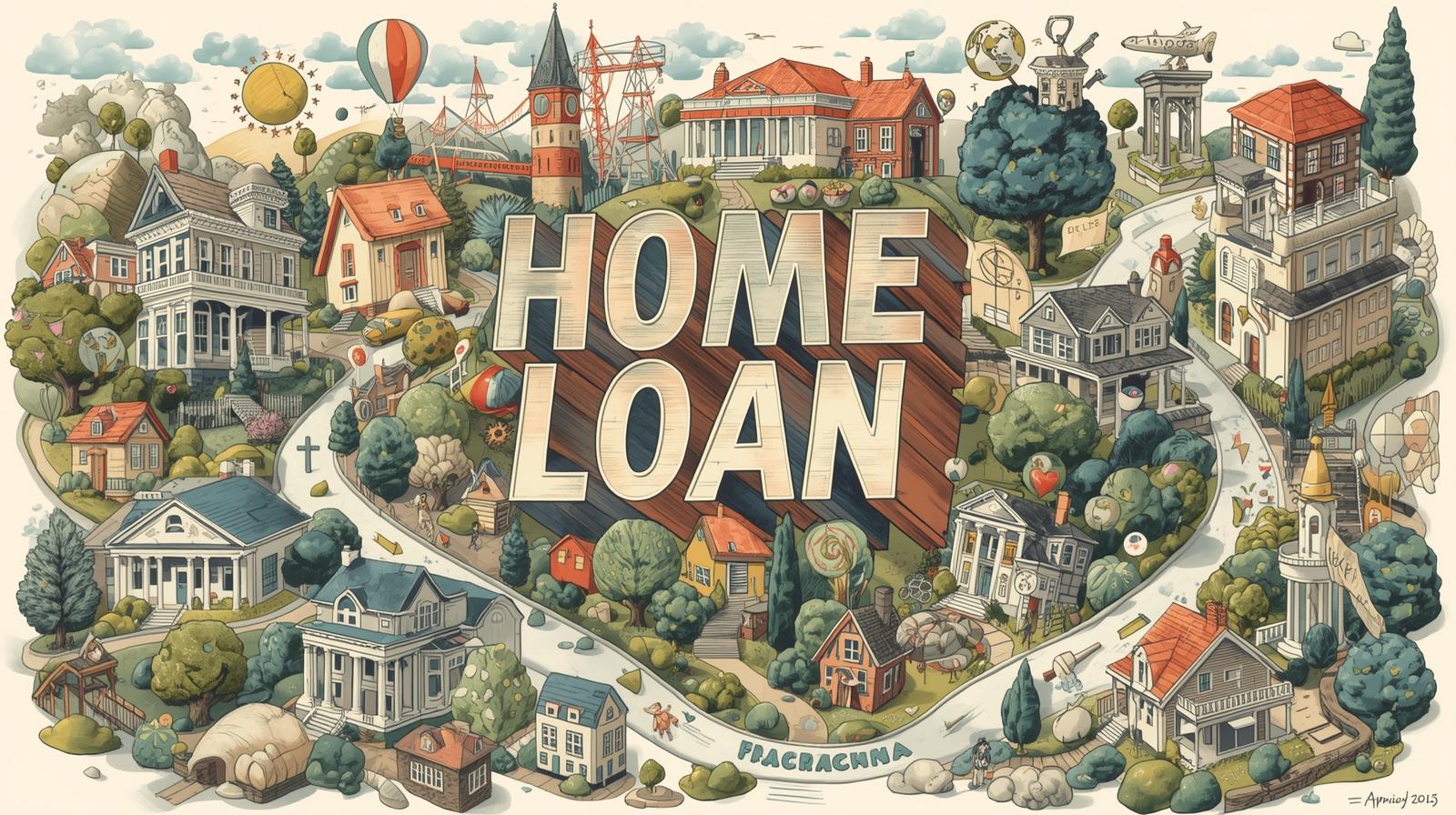
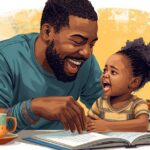




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません