【実例つき】教育費はいくら必要?無理なく準備する家計の見直し方

こんにちは。私は48歳、自営業で1児の父です。
ファイナンシャルプランナー2級・証券外務員1種・宅建士の資格を持っています。資格こそありますが、私自身も子どもが生まれるまでは「教育費ってなんとなくお金がかかるんだろうな」程度の認識しかありませんでした。
しかし、実際に子育てをしてみると、教育費は家計の中で大きな割合を占める出費です。
今回は、教育費にいくら必要なのか、そして無理なく準備するための家計の見直し方法を、私の実体験を交えながらお伝えします。
教育費はいくら必要?具体的な目安
文部科学省の調査によると、子ども1人にかかる教育費は進路によって大きく変わります。
公立に進学した場合(幼稚園〜大学まで)
- 幼稚園〜高校:およそ500万円前後
- 大学(国立・自宅通学):約500万円
合計:約1,000万円
私立に進学した場合(幼稚園〜大学まで)
- 幼稚園〜高校:およそ900万円以上
- 大学(私立・文系、自宅外通学):約700万円
合計:約1,600万円以上
つまり、進路によっては1,000万〜2,000万円近い教育費が必要になります。
私自身もこの数字を見て「正直に言うと、全部を貯金で賄うのは無理だな」と思いました。
我が家の実例|教育費の準備をどうしてきたか
私は子どもが小学校に入る前から「教育費専用口座」を作り、少額でもコツコツ積み立ててきました。
最初は月1万円からスタート。売上が良い月は3万円、厳しい月は1万円と変動させながらも「教育費には手をつけない」というルールを決めました。
さらに、
- ジュニアNISA(※現在は終了し、新制度に移行)を活用して投資信託を積立
- 学資保険は必要最低限(補償よりも貯蓄重視)で加入
結果として、子どもが中学生になる現在、ある程度の教育資金が蓄えられています。
完璧ではありませんが、「準備している」という安心感があるだけでも気持ちが楽になります。
無理なく教育費を準備する家計見直しのコツ
1. 家計の固定費を削る
教育費を貯めるためには「余裕資金」を作る必要があります。
私の実体験では、スマホを格安SIMに変えただけで年間7万円の節約に成功しました。その分をそのまま教育費口座に回しています。
- 通信費を削減(格安SIMや家族割を検討)
- 保険を整理(不要な特約や過剰な保障を削る)
- ローン金利を見直す(借り換えや繰り上げ返済)
固定費の見直しは、一度の決断で毎月の負担を減らせる効果的な方法です。
2. 「教育費専用口座」を作る
生活費と教育費を同じ口座で管理すると、いつの間にか使ってしまいます。
教育費専用の口座を作り、毎月自動振替で積み立てましょう。
たとえば、
- 月1万円 × 18年 = 216万円
- 月2万円 × 18年 = 432万円
少額でも「継続」が大きな力になります。
3. 積立投資を活用する
教育費は「いつまでに」「いくら必要か」が明確です。
長期の積立投資(つみたてNISAなど)を活用すれば、預金より効率的に資金を増やせます。
我が家では、教育費の半分を安全に貯金で、半分を投資信託で積み立てています。リスクを分散することで、安心と効率を両立させています。
4. 家族で「教育費の考え方」を共有する
意外と大切なのが、家族で教育費について話し合うことです。
「私立に行くのか、公立を基本とするのか」
「大学は自宅通学を前提にするのか」
進路の方向性を共有することで、必要な資金も変わります。
教育費の話題は重くなりがちですが、「子どもの夢を応援するため」という前向きなテーマとして話すとスムーズです。
まとめ|教育費は「早めに少しずつ」が安心の秘訣
教育費は想像以上に大きな負担ですが、次の3つを実践すれば無理なく準備できます。
- 固定費を削って余裕資金を作る
- 教育費専用口座で自動積立する
- 貯金と投資をバランスよく組み合わせる
私も最初は「そんなに大金を貯められるのか」と不安でした。
しかし、小さな積立をコツコツ続けることで、今では将来の教育費に対する心配が大きく減っています。
お父さんとしての安心感、そして家族の未来のために、今日から一歩を踏み出してみませんか?
まずは「教育費専用口座を作る」ことから始めるのがおすすめです。
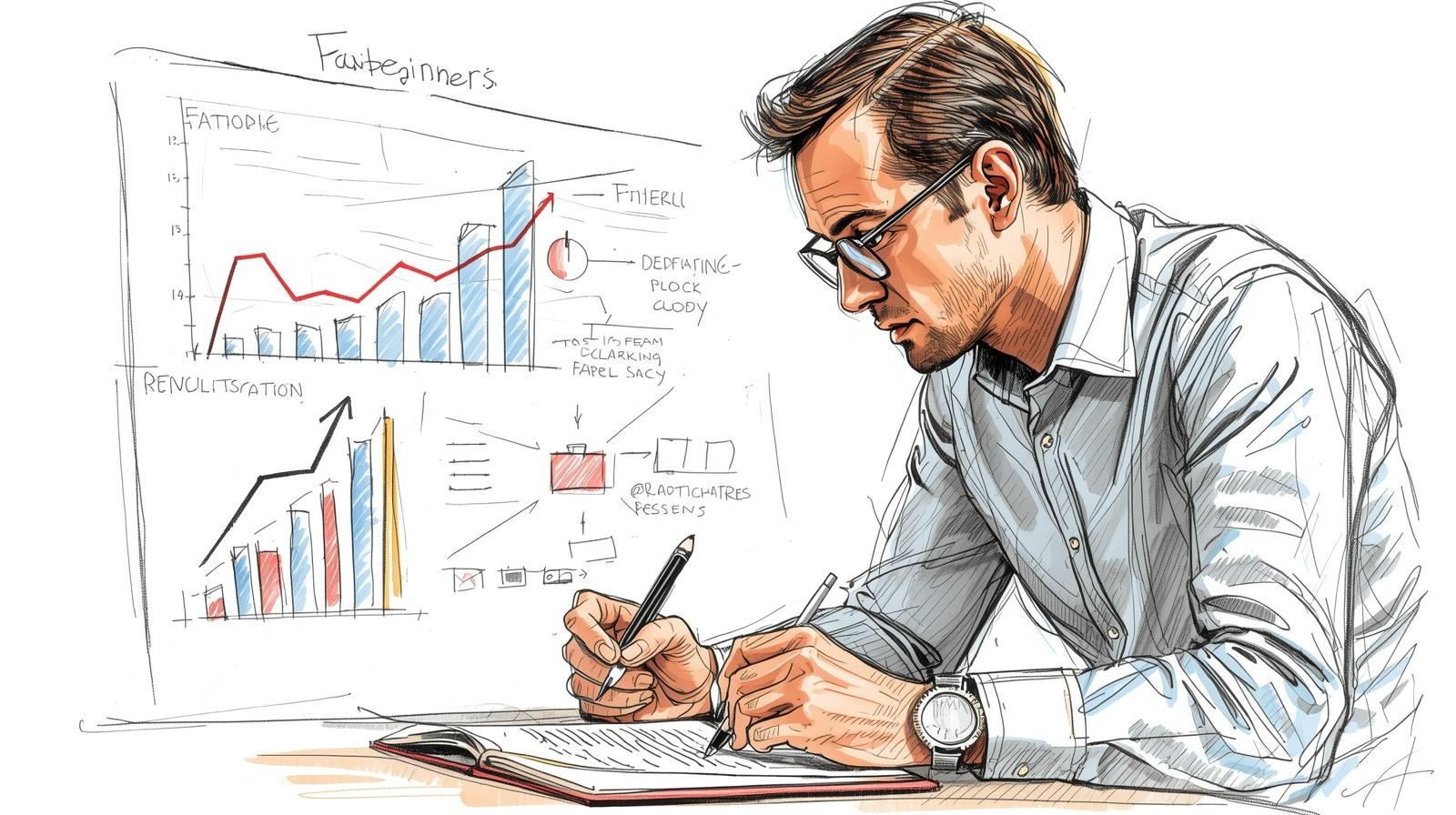
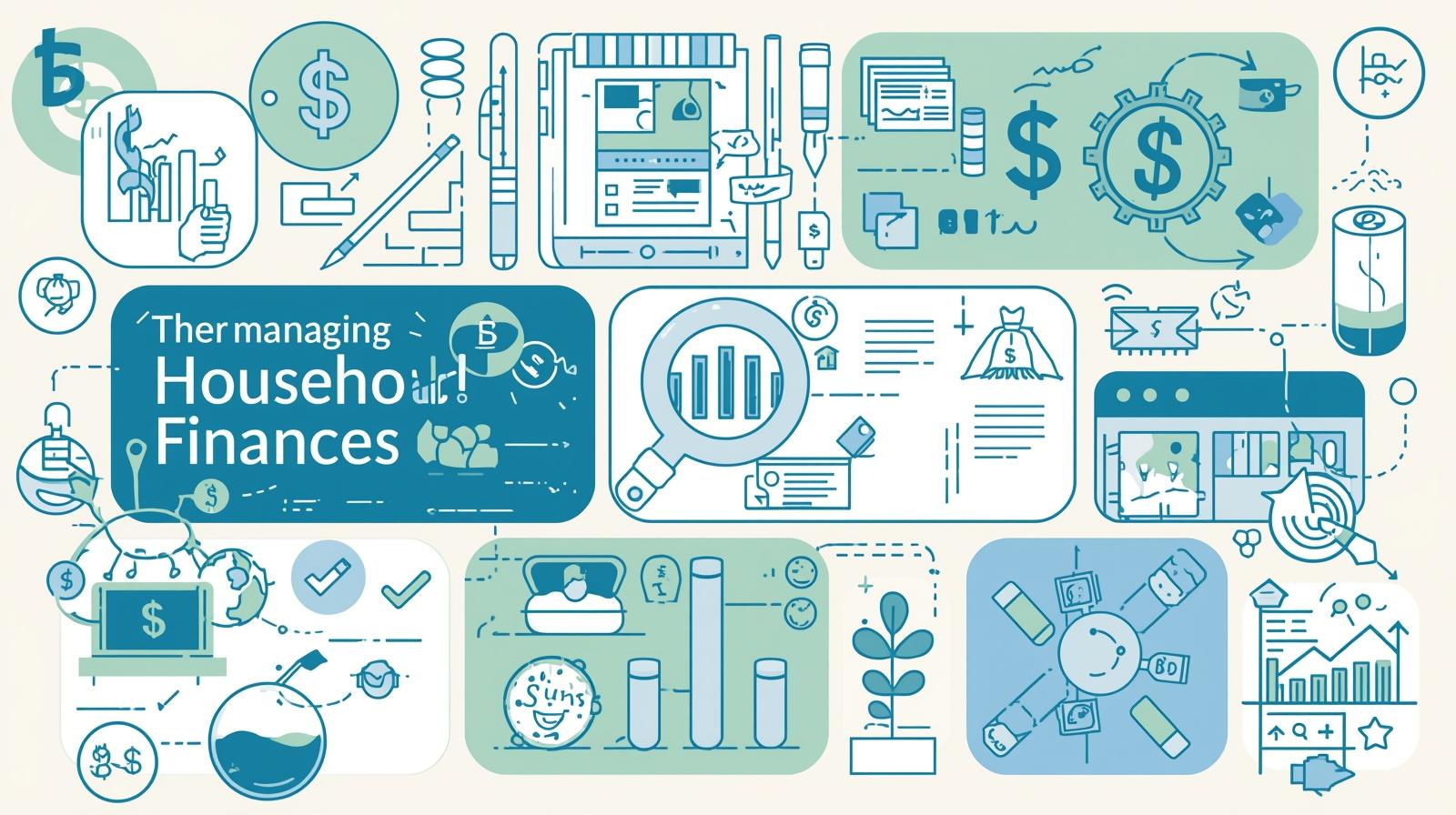

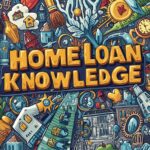
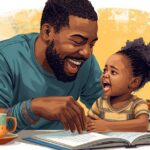


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません