固定費を下げる前に“浪費の正体”を見極める|見直しの順番が9割

こんにちは、
FP2級・証券外務員1種・宅建士の資格を持つ、自営業のお父さんです。
最近は「固定費を下げよう!」という言葉をよく耳にします。
もちろんそれは正しいのですが、
実は“順番を間違えると効果が出ない”んです。
家計の見直しで最初にやるべきことは、
「削る」ではなく「見極める」こと。
今回は、家計の浪費を見極めるコツと、
本当に下げるべき支出を見つける“順番の法則”をお話しします。
1. 節約が続かないのは「順番」が悪いから
家計を改善しようと意気込んで、
いきなり電気代・スマホ代・保険を見直す方が多いですが──
それは“2番目のステップ”なんです。
最初にやるべきは、「自分が何にお金を使っているか」を知ること。
家計の浪費を見極めずに節約を始めても、
ストレスがたまり、結局リバウンドしてしまいます。
2. 「浪費・消費・投資」を分けて考える
FPの基本ですが、支出は3種類に分類できます👇
| 区分 | 内容 | 例 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 消費 | 生活に必要なお金 | 食費・光熱費・家賃など | 生きるための支出 |
| 浪費 | 無くても困らない支出 | 衝動買い・サブスク過多・外食 | 一時的な満足 |
| 投資 | 将来の価値につながる支出 | 書籍・学び・健康・人脈 | 将来に利益をもたらす |
この3つを見分けることが、
“固定費見直しの前提”になります。
つまり──
浪費を「消費」と勘違いしている家計は、いくら節約しても改善しない。
3. 浪費を見抜くシンプルな質問
浪費かどうかを判断するには、
支出のたびにこの質問を自分にしてみてください👇
「これは“今日”のため?それとも“未来”のため?」
たとえば:
- コンビニでのつい買い → 今日の満足(=浪費)
- 本や資格の勉強代 → 未来の自分への投資
- 家族の食費 → 必要な消費
この「時間軸の視点」を持つと、
自然とお金の使い方が整理されていきます。
4. 家計見直しの正しい順番
では、実際に家計を整える“順番”を見ていきましょう。
【Step①】支出を3分類(消費・浪費・投資)する
まずは1ヶ月の支出をノートやアプリで分類します。
「使途不明金」が出てきたら、それが“浪費ゾーン”のサインです。
【Step②】浪費を削減する
いきなり固定費を触らず、まず“浪費”から削る。
カフェ代・外食・無駄なサブスクなど、月1万円でも減らせれば大きな成果です。
【Step③】固定費をリスト化して比較する
浪費を減らしてもまだ家計が苦しい場合、
ようやく固定費の番です。
代表的な見直しポイント👇
| 項目 | 平均支出 | 見直し後の例 |
|---|---|---|
| スマホ代 | 8,000円 | 格安SIMで2,000円 |
| 保険料 | 20,000円 | 必要保障に絞って8,000円 |
| サブスク | 5,000円 | 使っていないものを解約 |
| 電気・ガス | 10,000円 | 乗り換えで−1,500円 |
固定費は一度見直すと“自動的に節約できる”ため、
最初にやるよりも浪費削減後にやるほうが長続きします。
5. 「削る前に残す」も大切
節約というと、“削る”イメージがありますが、
実は“残す”も立派な節約です。
- 家族との外食 → 絆を深める「投資」
- 趣味に使うお金 → メンタルの健康維持
- 本や学びへの支出 → 将来の収入源
すべて切り詰めると、
“お金は貯まるけど心がすり減る”状態になります。
大切なのは、
「本当に大事なものを残し、それ以外を削る」
これが、続く節約の鉄則です。
6. 見直し後にやるべき2つのこと
固定費と浪費を整えたら、
次にやるべきは“流れを作る”ことです👇
① 節約した分を「貯蓄・投資」へ自動移動
たとえば、スマホ代を月6,000円下げたら、
その6,000円を自動で貯蓄やNISA積立に回す。
節約の成果を“形に残す”ことで、モチベーションが続きます。
② 家計の「定期点検」をする
1年に1回は、
保険・通信・サブスクを見直す日を“家計の棚卸しデー”に設定。
年末や誕生日など、続けやすい日を決めると習慣化できます。
7. 「節約で失敗する人の共通点」
長年、家計相談をしてきて感じるのは、
節約がうまくいかない人ほど、数字より気持ちで動いているということ。
「これぐらいならいいか」
「今月はちょっと頑張ったから」
感情で支出を決めてしまうと、
節約は続かず、気づけば元に戻ってしまいます。
数字で管理するだけで、人は冷静になります。
家計簿アプリやスマホメモでも十分です。
“見える化”は、最大の節約。
8. まとめ:「削る順番」を間違えないこと
固定費を下げることは、家計改善の王道です。
でも、本当に大切なのは削る順番です。
1️⃣ 浪費を見極めて減らす
2️⃣ 固定費を比べて下げる
3️⃣ 節約分を貯蓄・投資に回す
この流れを作るだけで、
「頑張らなくてもお金が残る家計」になります。
💬 今日のひとこと
「節約は我慢じゃない。“選ぶ力”を鍛えること。」


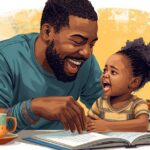




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません