貯金ゼロ家庭がやりがちな5つの勘違い|“余ったら貯める”は危険

こんにちは、FP2級・証券外務員1種・宅建士の資格を持つ、自営業のお父さんです。
日々、私のまわりでもよく聞く言葉があります。
それは──
「うちは貯金する余裕がないんです」
実は、貯金ゼロ家庭の多くは“収入の少なさ”よりも、考え方のズレが原因なんです。
今回は、そんな「お金が貯まらない5つの勘違い」と、
今すぐ始められる“貯まる家計”への切り替え方をお話しします。
1. 「余ったら貯める」は一生余らない
最も多い勘違いがこれです。
「毎月の生活費を払って、余ったら貯金しよう」
……残念ながら、これでは一生“余りません。
人は収入に合わせて生活を広げてしまう生き物。
手取りが増えても、外食・サブスク・ちょっとした贅沢で支出が自然に膨らみます。
貯金は「余り」ではなく「先取り」が鉄則。
給料が入ったら、まず貯金(または投資用)口座に自動で移す。
たとえ月5,000円でも、ルール化しておけば自然と貯まります。
2. 「節約=我慢」だと思っている
節約という言葉を聞くと、「我慢」「つらい」と感じる人が多いですが、
本当の節約は“選択”を賢くすること”です。
たとえば、同じスマホプランでも
- 大手キャリア → 月8,000円
- 格安SIM → 月2,000円
これで月6,000円、年間72,000円の差。
これは“我慢”ではなく、“情報を知って選んだ結果”です。
「節約=収入を増やすのと同じ」
そんな意識に変えるだけで、お金の流れが大きく変わります。
3. 「保険に入っているから安心」
これもよくある誤解です。
保険は“備え”ではありますが、貯蓄や投資の代わりではありません。
たとえば、月2万円の保険料を20年払い続けると480万円。
その中で「本当に必要な保障」はいくらでしょうか?
見直してみると、「過剰保障」「不要な特約」がついているケースが多くあります。
「万が一」に備える前に、「今」を圧迫していないかを見直すのが大切です。
浮いた保険料を貯蓄やNISA積立に回せば、老後資金の不安はずっと減ります。
4. 「ボーナスで調整すれば大丈夫」
これも危険な発想です。
ボーナスは“ご褒美”ではなく、“変動リスク”です。
経済状況・勤務先の業績・社会情勢──どれをとっても、
ボーナスは安定した収入とは言えません。
もしボーナスを家計の「前提」にしていると、
支出が固定化し、ボーナスが減った瞬間に赤字になります。
ボーナスはあくまで“臨時収入。
使うよりも、「年1回の家計見直し」や「特別支出の備え」に充てるのが賢明です。
5. 「貯金は銀行が安全」
昔は正解でした。
でも今の日本では、銀行預金は安全ではあるが増えないのが現実。
金利0.2%では、100万円を1年預けても利息は2,000円。
そこから税金が引かれ、実質1,600円ほどしか増えません。
一方で、物価は上昇中。
実質的には“目減りしている”ことになります。
“安全”を選びすぎると、“未来のリスク”を抱える──
それが今の時代の家計構造です。
貯まる家計に変わるための3ステップ
ここまでの“勘違い”を踏まえて、
今日からできる「貯まる家計」への3つの行動を紹介します👇
① 収入の10%を先取り貯金に
給料が入ったら、まず貯金用口座に自動振替。
ポイントは「考えずに貯まる仕組み」を作ること。
② 固定費を1年間で3万円カット
スマホ・保険・サブスクを見直すだけで簡単に達成できます。
浮いたお金はそのままNISAや積立に。
③ 銀行預金の一部を“お金を働かせる口座”へ
つみたてNISA・iDeCo・高配当ETFなど、
少額でも“お金が増える場所”に分散させましょう。
まとめ:「貯められない」は“性格”ではなく“仕組み”の問題
多くの人が「自分はお金の管理が苦手」と言います。
でも実際は、“仕組み”を整えていないだけなんです。
「余ったら貯める」ではなく、「貯めたら使う」。
この順番を変えるだけで、家計は驚くほど安定します。
💬 今日のひとこと
「お金は“気合い”では貯まらない。“仕組み”で貯める。」




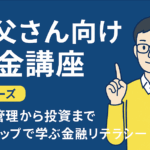


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません