損しないための上限額の計算方法|ふるさと納税でいくらまでお得?
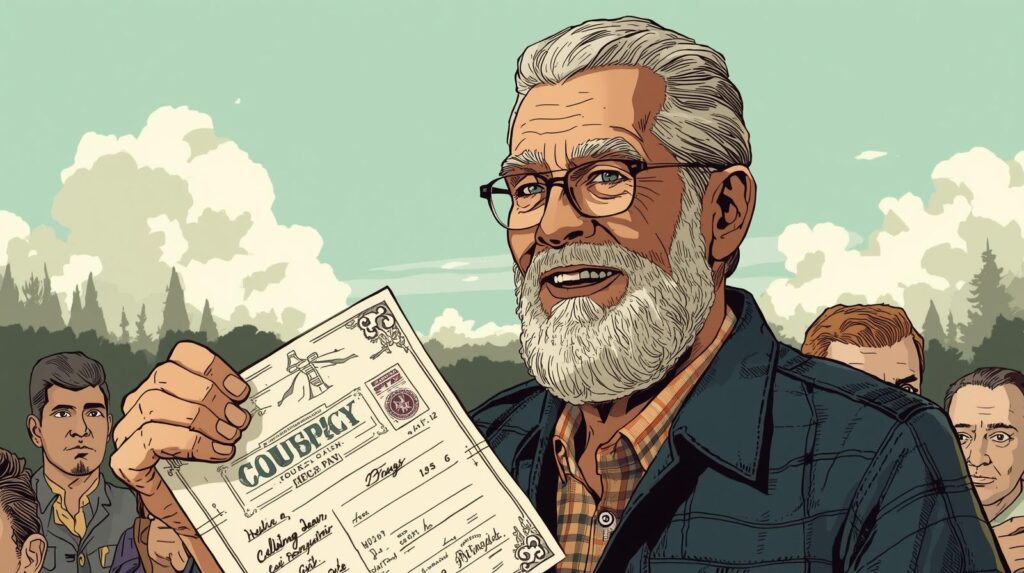
こんにちは。48歳、自営業で一家を支える父です。
私はファイナンシャルプランナー2級・証券外務員1種・宅建士の資格を持ち、「お父さんのための家計管理と節税の知恵」を発信しています。
前回の記事では、ふるさと納税が「実質2,000円で特産品をもらいながら節税できる制度」だとお伝えしました。
ただし、ここで大切なのが 「上限額」。
この上限を超えて寄付してしまうと、控除されずに自己負担が増える=損してしまうんです。
今回は、初心者のお父さんでも簡単に理解できるように、
ふるさと納税の「上限額の考え方」と「計算の仕方」をわかりやすく解説します。
1. なぜ上限額があるの?
ふるさと納税では、寄付したお金が所得税・住民税から控除(減額)されますが、
その控除には上限が設定されています。
これは、「納税額の範囲内で寄付する」ことを前提にしているからです。
つまり、上限を超えた分は**単なる寄付(税金控除なし)**になってしまうんですね。
👉 だからこそ、「上限を知ること」がふるさと納税の第一歩です。
2. 上限額を決める3つの要素
上限額は、主に次の3つの要素で決まります。
1️⃣ 年収
2️⃣ 家族構成(配偶者・子ども)
3️⃣ 住民税の金額(=所得税率)
たとえば、年収が同じでも、
・専業主婦の妻と子どもがいる人
・共働きで子どもがいない人
では、控除額が変わります。
つまり、「家族の扶養状況」と「所得税率」によって上限が変動します。
3. 年収別の上限額の目安
お父さんがパッと見てイメージしやすいように、
「夫婦+子ども1人(高校生)」という一般的な家庭を例にした上限目安を示します。
| 年収 | 控除上限額の目安 |
|---|---|
| 400万円 | 約4〜5万円 |
| 500万円 | 約6万円 |
| 600万円 | 約7〜8万円 |
| 700万円 | 約9万円 |
| 800万円 | 約10万円 |
| 1000万円 | 約13万円 |
(※共働き・独身の方はやや上がる傾向があります)
👉 この範囲内で寄付すれば、「自己負担2,000円」で済みます。
4. 簡単な目安計算式
おおまかな上限を知りたい場合は、次の計算式が便利です。
上限額 ≒ (年収 − 住民税非課税分) × 20% × 控除率
ざっくりですが、「年収の2%前後」が上限の目安になることが多いです。
たとえば
- 年収500万円 × 2% ≒ 10万円
→ 控除上限は約6〜8万円ほど - 年収800万円 × 2% ≒ 16万円
→ 控除上限は約10万円ほど
もちろん正確に出すには税額計算が必要ですが、
「だいたいこのくらい」と把握しておけば十分です。
5. 正確に知るならシミュレーションを使おう!
ふるさと納税サイトには、便利な「上限額シミュレーター」があります。
給与明細にある以下の項目を入力すれば、かなり正確な金額が出せます。
✅ 年収
✅ 扶養家族の人数
✅ 住民税控除額(前年分)
👉 お父さんの場合は、12月の源泉徴収票が手元にあれば、すぐに入力できます。
6. 損しないためのチェックポイント3つ
ふるさと納税をお得に使うために、次の3つを意識しておきましょう。
(1)上限額ギリギリを狙わない
→ 数千円余裕を持って寄付するのが安心です。
(控除が反映されないトラブルを防げます)
(2)複数の収入源がある場合は注意
→ 自営業・副業収入などがある場合は、住民税が変わるので、申告時にしっかり確認を。
(3)共働きなら「それぞれが」ふるさと納税できる
→ 共働き家庭は、夫婦それぞれに上限額が設定されています。
2人で分けて寄付すれば、さらにお得!
7. ふるさと納税の節税効果を数字で見る
たとえば、年収600万円・子ども1人の家庭の場合:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 寄付額 | 70,000円 |
| 自己負担 | 2,000円 |
| 税金控除 | 68,000円(翌年減税) |
| 返礼品 | 約20〜30種類から選択可(お米・肉・ビールなど) |
👉 つまり、「実質2,000円」で、数万円分の特産品がもらえる上に税金も安くなる。
これがふるさと納税最大の魅力です。
8. 私自身の活用例
私は上限約7万円の範囲で、毎年4〜5自治体に寄付しています。
- 北海道:冷凍ホタテ
- 新潟:お米
- 宮崎:鶏の炭火焼
- 静岡:クラフトビール
返礼品が届くたびに家族で楽しみながら、「税金を賢く使えている」と実感します。
9. まとめ|上限を知ることが最大の節税テクニック
今回のポイントをまとめると:
- ふるさと納税には「控除上限額」がある
- 上限を超えると損をする(自己負担が増える)
- 目安は「年収の約2%前後」
- 正確にはシミュレーションを活用
- 共働きなら2人分の上限を活用できる
お父さん、ふるさと納税は「節税×家計改善」の最強コンビです。
まずは自分の上限額を把握して、今年の寄付計画を立ててみましょう。
12月のボーナス時期は寄付が集中します。
今から準備しておけば、年末ギリギリで焦ることなく、ゆとりを持って活用できます。


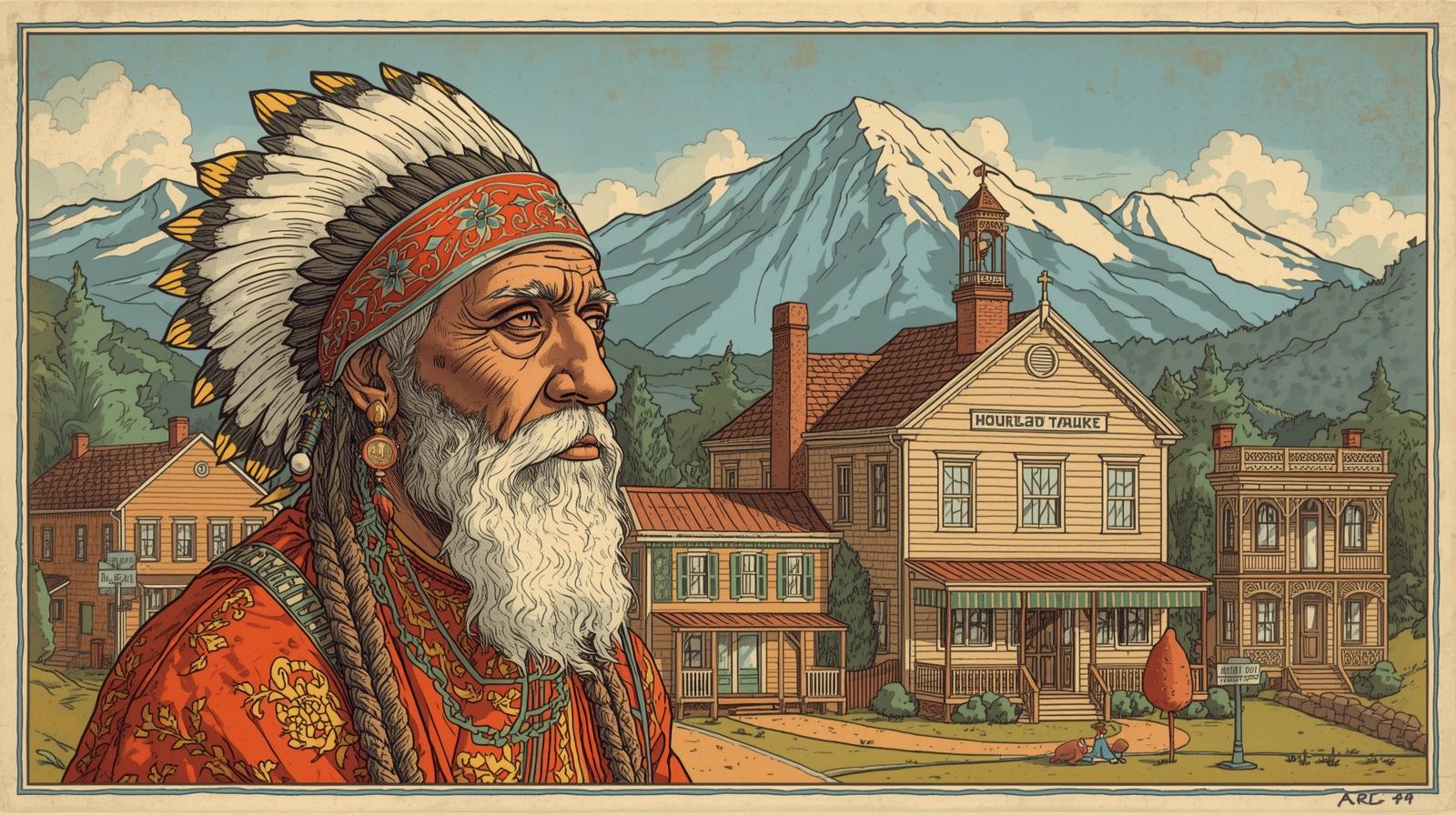



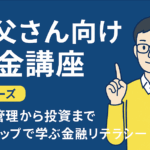

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません